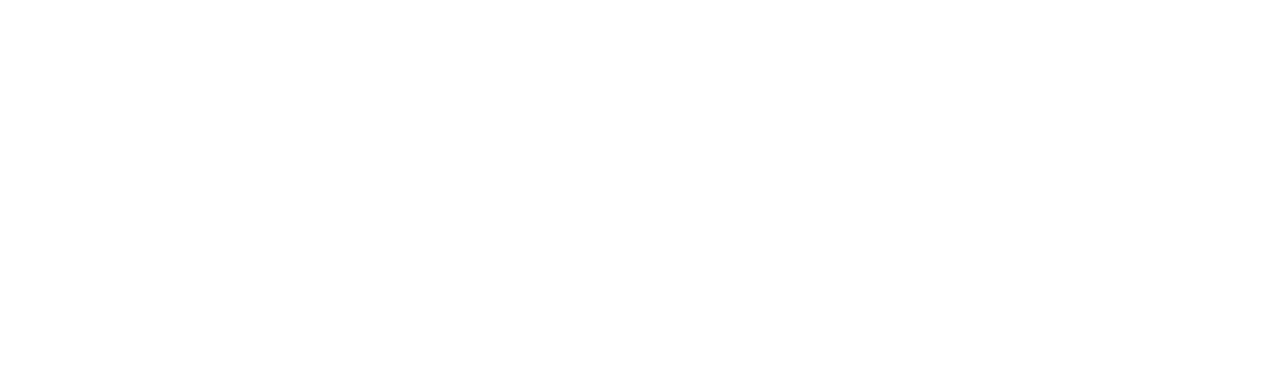
Activities
活動実績
活動実績一覧
活動実績
- 2025年12月23日 連載エッセイ 音楽学者のつれづれ 第5回
- 2025年12月23日 連載講座 カトリック教会の音楽 第2回
- 2025年12月09日 放送大学東京文京学習センター公開講演会のご案内
- 2025年12月09日 「音楽から人間を考える会」第4回を開催します。
- 2025年11月13日 「⾳楽から⼈間を考える会」第3回を開催します。
- 2025年10月9日 「⾳楽から⼈間を考える会」第2回を開催します。
- 2025年9月26日 連載講座 カトリック教会の音楽 第1回
- 2025年9月24日 連載エッセイ 音楽学者のつれづれ 第4回
- 2025年9月12日 「⾳楽から⼈間を考える会」第1回を開催します。
- 2024年10月15日 「音楽から人/ひとを考える会」第33回を開催します。
- 2024年9月18日 「音楽から人/ひとを考える会」第32回を開催します。
- 2024年7月17日 「音楽から人/ひとを考える会」第31回を開催しました。
- 2024年5月20日 コール淡水・東京 第11回定期演奏会を開催します。
- 2024年5月15日 「音楽から人/ひとを考える会」第30回を開催します。
- 2024年3月20日 「音楽から人/ひとを考える会」第29回を開催します。
- 2024年3月17日 放送大学 東京文京学習センター 永原ゼミ 成果発表演奏会を開催しました。
- 2024年2月10日 放送大学 東京文京学習センター 公開講演会を開催しました。
- 2023年12月19日 「音楽から人/ひとを考える会」第28回を開催します。
- 2023年11月14日 「音楽から人/ひとを考える会」第27回を開催します。
- 2023年10月18日 「音楽から人/ひとを考える会」第26回を開催します。
- 2023年10月18日 「音楽から人/ひとを考える会」第25回を開催しました。
- 2023年9月6日 「音楽から人/ひとを考える会」第24回を開催しました。
- 2023年7月18日 「音楽から人/ひとを考える会」第23回を開催します。
- 2023年6月26日 カトリック浅草教会『教会報』5月号、6月号に「教会と音楽」第17回、第18回を掲載しました。
- 2023年6月26日 東洋音楽学会東日本支部第135回例会でオンライン発表します。
- 2023年6月26日 講演会に登壇しました。放送大学東京足立学友同窓会主催
「音楽をアンサンブルから理解するー民族音楽学が切り拓いた音楽の学びー」 - 2023年6月26日 演奏会に出演しました。「永井和子Presenz habe Dank 2! 〜真の歌声を求めて〜」
- 2023年6月20日 「音楽から人/ひとを考える会」第22回を開催します。
- 2023年5月10日 「音楽から人/ひとを考える会」第21回を開催します。
- 2023年4月12日 「音楽から人/ひとを考える会」第20回を開催します。
- 2023年3月9日 「音楽から人/ひとを考える会」第19回を開催します。
- 2023年2月14日 「音楽から人/ひとを考える会」第18回を開催します。
- 2023年1月17日 「音楽から人/ひとを考える会」第17回を開催します。
- 2022年12月15日 「音楽から人/ひとを考える会」第16回を開催します。
- 2022年10月17日 「音楽から人/ひとを考える会」第15回を開催します。
- 2022年9月13日 「音楽から人/ひとを考える会」第14回を開催します。
- 2022年8月12日 「音楽から人/ひとを考える会」第13回を開催します。
- 2022年7月15日 「音楽から人/ひとを考える会」第13回を開催します。
- 2022年6月13日 「音楽から人/ひとを考える会」第12回を開催します。
- 2022年5月20日 「音楽から人/ひとを考える会」第11回を開催します。
- 2022年4月18日 「音楽から人/ひとを考える会」第10回を開催します。
- 2022年3月15日 「音楽から人/ひとを考える会」第9回を開催します。
- 2022年2月15日 連載エッセイ 音楽学者のつれづれ 第3回
- 2022年2月15日 「音楽から人/ひとを考える会」第8回を開催します。
- 2022年1月17日 「音楽から人/ひとを考える会」第7回を開催します。
- 2021年12月13日 「音楽から人/ひとを考える会」第6回を開催します。
- 2021年11月30日 連載エッセイ 音楽学者のつれづれ 第2回
- 2021年11月30日 連載講座 カトリック教会と音楽 第2回
- 2021年11月12日 「音楽から人/ひとを考える会」第5回を開催します。
- 2021年10月27日 連載エッセイ 音楽学者のつれづれ 第1回
- 2021年10月27日 連載講座 カトリック教会と音楽 第1回
- 2021年10月14日 「音楽から人/ひとを考える会」第4回を開催します。
- 2021年9月8日 「音楽から人/ひとを考える会」第3回を開催します。
- 2021年7月2日 「音楽から人/ひとを考える会」第2回を開催します。
- 2021年6月4日 「音楽から人/ひとを考える会」がスタートします。
- 2021年6月4日 放送大学東京文京学習センターの永原ゼミが再スタートいたします。
- 2021年6月4日 放送大学面接授業の閉講
- 2021年4月1日 ホームページを公開しました。
2025年12月23日 連載エッセイ 音楽学者のつれづれ 第5回
曆と音楽(その2)2025年12月23日 連載講座 カトリック教会の音楽 第2回
カトリック教会の音楽(第2回)放送大学東京文京学習センター公開講演会のご案内
2026年2月7日(土)14時〜16時に、下記の公開講演会を開催いたします。(対面)
会場:放送大学東京文京学習センター 多目的講義室1
講師:永原恵三
テーマ:「西洋バロック音楽の歌曲 —J.S. バッハとG.F.ヘンデルに至る道—」
概要:
西洋のバロック音楽は基本的に1600年頃から1750年頃のヨーロッパで盛んになった音楽様式と規定されます。この時代はヴィヴァルディやバッハ、ヘンデルに至って様々な器楽曲が隆盛したことで知られています。本講演では、こうした華やかな器楽曲で見えなくなっている声楽曲を取り上げます。感情表現の豊かなオペラや歌曲、ラテン語だけでなく自国語での宗教的歌曲、そしてオラトリオへと発展した声楽曲の魅力について、歌曲を中心にお話しします。また、カッチーニ、シュッツ、パーセル、ヘンデルなどの作品を実際に演奏いたします。
聴講希望の方はURL内の申込フォームに記入してお申込みください。
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/bunkyo/news/2025/12/03111544.html
「音楽から人間を考える会」第4回を開催します。
「音楽から人間を考える会」は「音楽から人/ひとを考える会」を発展して学会組織とした研究会です。詳細は下記のプログラムをご覧ください。会員以外で参加を希望される方は、以下のブログに掲載の事務局まで一旦ご連絡ください。
https://otokarahito.wordpress.com/
日時:2025年12月17日(水)20時〜22時
形式:Zoomによるオンライン開催(URLは参加申込者にお伝えします、)
研究発表:根来章子(和光大学)
題目:セレスタン・フレネの教育思想と音楽実践:聴く活動に焦点を当てて
要旨
本研究の⽬的は、セレスタン・フレネ(Célestin Freinet, 1896-1966)の教育思想と⾳楽実践の様相を、「聴く活動」から明らかにすることである。
フレネは、公⽴⼩学校で教師を務めていた1920年代から、教師主導の知識注⼊型教育を批判し、⼦どもの⽣活や興味から始まる⾃由な表現を基盤に置いた教育を追究し始めた。1935年には南仏ヴァンスでフレネ学校を開校し、「⾃由テキスト」や「学校間通信」を始めとする独⾃の教育技術と学習材を開発、展開した。これらは⼦どもが⽣活の中で⾒つけた関⼼を⾃由に表現し、互いに批評し合うことで、学習の個別化と協同化を図るものであった。
フレネ学校では⾳楽教育も実践されてきた。学校⾳楽教育について、フレネは他の領域と同様に「⾃由で総合的な表現がすべての活動の基礎である」と述べ、⾳楽も「⾃由表現」という基本的原理の地平上にあることを表明している。
1951 年、フレネに賛同する教師らによる教育研究機関、ICEM(Institut Coopératif del'Ecole Moderne 現代学校協同研究所)が組織された。フレネ教育は、フレネが単独で培ったものではなく、賛同者による実践の蓄積で形作られている。ICEM には⾳楽部⾨があり、実践研究が続けられてきた。その⼤きな柱は、楽器作りや即興演奏といった⾳を⽣み出す活動である。⼀⽅で、特に学校創設初期には、レコードを活⽤した「聴く活動」も盛んに⾏われ、⾳楽的素養に乏しい教師の⼿⽴てとなった。1950 年代に⼊ると、鑑賞⽤レコードの解説冊⼦が出版される⼀⽅、この⼿法への批判も現れる。さらに現代では、録⾳媒体を⽤いた作品鑑賞そのものがほとんど扱われなくなっていることが出版物からうかがえる。聴くことの重要性は現代のフレネ教育においても継承されているものの、その取り扱い⽅には何らかの変遷があったと考えられる。しかし、この変遷を分析した研究は⾏われていない。また、フレネの⾳楽教育を歴史的、網羅的に整理した研究も⾒当たらない。
そこで本発表では、フレネの「聴く活動」に焦点を当て、その実践の変遷を整理し、フレネ教育が「聴くこと」をどのように扱ってきたかを明らかにする。レコードを聴く活動は、現代の学習指導要領における鑑賞領域に位置付けられる。フレネが⽬指す⼦どもによる主体的な学習構築は、現代でも重要性を増しており、鑑賞活動と⼦どもの主体性をどのように結びつけられるかという現代的課題を検討する⼿がかりとしたい。
なお本発表は、⽇本⾳楽教育学会第56回⻑崎⼤会(2025年11⽉8⽇)にて同タイトルで発表した内容に加え、質疑応答で明らかになった課題を含めて提⽰するものである。
キーワード:フレネ教育、聴く活動、⾳楽科教育、鑑賞、主体的な学習
「⾳楽から⼈間を考える会」第3回を開催します。
「音楽から人間を考える会」は「音楽から人/ひとを考える会」を発展して学会組織とした研究会です。詳細は下記のブログをご覧ください。
会員以外で参加を希望される場合は、ブログに掲載の事務局まで一旦ご連絡ください。
https://otokarahito.wordpress.com/
日時:2025年11月19日(水)20時〜22時
形式:Zoomによるオンライン開催(URLは参加申込者にお伝えします)
研究発表:岩本由美子
題目:
プラハおよびチャースラフにおける J.L. ドゥセク史料現地調査:地域記憶と自筆書簡の分析
要旨: 2025 年 8 月、チェコ共和国のプラハとチャースラフにおいて、ヤン・ラディスラフ・ドゥセク(Jan Ladislav Dussek, 現地表記 Dusík, 1760-1812)に関する現地調査を実施した。研究対象のドゥセクは 18 世紀末から 19世紀初頭に活躍したボヘミア出身の音楽家である。本調査では、プラハの国立図書館音楽部門や国立音楽博物館、チャースラフ市立博物館、その他のドゥセク関連施設の協力を得て、地域に残る収蔵資料や記念事業の記録を確認した。
ドゥセクの初期活動については、ベルギーおよびオランダで演奏・出版を開始したことが先行研究において指摘されており、故郷にも自筆草稿や未刊行作品が残存する可能性を想定したが、そのような資料は確認できず、現存するのは西ヨーロッパ各地から収集された初版や再版が中心であった。
一方で、プラハの国立図書館および国立音楽図書館において、1810 年および 1811 年付の未発表自筆書簡を確認したことは特筆に値する。一通はパリ在住の医師ワーグナー宛で、差出人住所として「ベネヴェント宮殿」(タレーラン公邸)が記されており、晩年のドゥセクが政治貴族層との接点を持っていた事実を補強する。もう一通は、パリの音楽出版社カミーユ・プレイエル宛で、書簡には複数の作品名と女性献呈者が記されている。これらの作品と献呈先、さらに出版や演奏の需要を分析することで、当時の音楽家たちの市場戦略を読み取ることができる。また、この分析は、出版流通と演奏実践の関係を考察する手掛かりにもなる。
さらに、出身地チャースラフでは、博物館に残る周年行事の資料や、地元アートスクール内のドゥセク・ギャラリー、ドゥセク劇場、生家跡地の記念レリーフなどを確認した。一部の資料は、施設の設立や記念事業のために国外から集められたもので、地域社会が意図的に「ドゥセクの記憶」を形づくってきたことがうかがえる。特に、共産主義時代に記念行事が行われたことは、政治体制が変わっても、ドゥセクが地域で大切にされてきたことを示すだろう。本調査では、西欧の出版物や作品だけでは見えない、地域でのドゥセクのかかわり方を明らかにした。地域の資料と未発表の書簡を合わせて確認することで、ドゥセクの歴史的な足跡をより詳しく知ることができる。
キーワード: J.L. ドゥセク(Dusík) 自筆書簡 楽譜出版 出生地チャースラフ 地域的記憶
「⾳楽から⼈間を考える会」第2回を開催します。
「音楽から人間を考える会」は「音楽から人/ひとを考える会」を発展して学会組織とした研究会です。詳細は下記のブログをご覧ください。
会員以外で参加を希望される場合は、ブログに掲載の事務局まで一旦ご連絡ください。
https://otokarahito.wordpress.com/
日時:2025年10月15日(水)20時〜22時
形式:Zoomによるオンライン開催(URLは参加申込者にお伝えします)
研究発表:猶原和子(元江戸川大学、江戸川大学名誉教授)
題目と要旨:
題目 島根県津和野町の「子鷺踊り」にみる伝統文化の継承と課題」
要旨
津和野町彌榮神社の大祭で行われる 「鷺舞」 は 「風流踊」の一つとしてユネスコ無形文化遺産として記載されている。 大人の男性陣による 「鷺舞」 に彩を添え、 子ども達自身が喜んで踊り故郷の思い出となる伝統芸能が必要だと 1958 年に制作されたのが「子鷺踊り」であし、私財を投じて「子鷺踊り」」の普及に勉め町の発展に貢献した。
歌は田中良作詞・坂本良隆作曲で、4 番までの歌詞のすべてに「鷺舞神事」に関わる文言が入っており、衣装や西崎真由美による振り付けも 「鷺舞」 の動きを意識して創作されている。原曲は箏・篠笛、鉦と歌で制作されていたが、2009 年に地元の小学 3 年生の歌とリコーダーを中心にした構成に変更しており、これについては賛否両論がある。 彌榮神社の大祭(7 月 20 日の渡御、27 日の還御)への参加のほかに、TV や多くの催しから依頼を受けて出演しており、小学 4 年社会科の表紙にも用いられている。設立時は女子のみが対象であったが、現在は男女を問わず小学校 3 年~6 年に希望を募っている。例年 60 名が 2 列の行列で町内を回り踊ってきたが、今年度は出演者が 13 名にまで減り行列が困難となり、室内でステージ形式の踊りに変更した。
「子鷺踊り」の衣装管理や踊りの指導運営は、 「子鷺踊り保存会」が会費と助成金・寄付をもとに行っている。津和野小学校ではふるさと教育の一環として 7 月の朝の歌に「子鷺踊りのうた」 を取り上げている。 4 年前までは総合学習でも 「子鷺踊り」を取り上げていた。今年参加した子どもたちに参加理由を尋ねると、両親や祖父母に勧められた子が半数、「友達といっしょに出たかった」「服装がかわいいから」「去年やって楽しかったから」という理由の子もいた。踊った後は皆満足した表情であった。
今後の課題としては過疎化による子どもの激減、合併に伴う町民の意識の隔たりが挙げられる。 また、ここ数年の猛暑もあり、 13 時の開始時刻や踊る場所の検討も迫られている。さらに指導者の後継者問題も深刻である。自営業の女性が中心だったが 「鷺舞保存会」の関係者減少とも絡み、 難しい状況も起きている。 今後、 新しく移住してきた方々との連携や社会教育での活用を図ることがさらに必要だと思われる。
キーワード: 伝統芸能 鷺舞 保存会 過疎 ふるさと教育
2025年9月26日 連載講座 カトリック教会の音楽 第1回
カトリック教会の音楽(第1回)連載エッセイ 音楽学者のつれづれ 第4回
第4回 曆と音楽(その1)「⾳楽から⼈間を考える会」第1回を開催します。
「⾳楽から⼈間を考える会」は「⾳楽から⼈/ひとを考える会」を発展して学会組織とした研究会です。詳細は下記のブログをご覧ください。
会員以外で参加を希望される場合は、ブログに掲載の事務局まで⼀旦ご連絡ください。
https://otokarahito.wordpress.com/
⽇時:2025 年 9 ⽉ 17 ⽇(⽔)20 時〜22 時
形式:Zoom によるオンライン開催(URL は参加申込者にお伝えします)
基調講演:永原恵三(本会会⻑)
題⽬と要旨:
題⽬:⾳楽と⼈間と時間−曆から読み取る⼈間の営み−
永原恵三(お茶の⽔⼥⼦⼤学名誉教授、放送⼤学客員教授)
要旨
本講演は「⾳楽から⼈間を考える会」の発⾜にあたり、⾳楽と⼈間そして時間の関係について、様々な⼈間の⽣活に固有に存在する「曆」を事例として、そこから読み取ることのできる⼈間の営みを考えることを⽬的としている。
具体的にはカトリック教会における典礼暦とミサ聖祭の「感謝の祭儀」を取り上げ、固有唱の「奉納の歌」、叙唱、「感謝の賛歌 Sanctus」および奉献⽂について考察する。奉献⽂にはキリストの最後の晩餐において語られた⽂⾔が含まれ、ミサ聖祭の中⼼部分が唱えられる。この⼀連の流れのなかには、⼤きく典礼暦という⼀年の周期的時間のサイクルがある。また、そこでは、奉献⽂における「記念(アナムネーシス)」という⾔葉に収斂される継続的時間と時間の超越とが並存している。ここにミサ聖祭が持つ時間性、すなわち時間とともに⽣きる⼈間のありかたと、「神」という時間を越えた存在との接点を⾒出すことができる。
⾳楽は「時間の芸術」と呼ばれるが、これは単に⻄洋⾳楽の⼤作曲家の作品⾄上主義で⽣み出された表現であり、「芸術」⾃体もまた同様の前提にある。しかし、19 世紀を中⼼とした⻄洋芸術⾳楽は、ヨーロッパの⼀地⽅のかつ⼀部の階級社会で流⾏したごく地域的⾳楽にほかならない。⾳楽が時間の芸術である、という命題は⼀度解体しなければならないだろう。
⾳楽は諸⾳楽(musics)へ、芸術は技術(テクネー)へ、そして時間は⼈間が背負うべき様々な営みが実現される「死へと向かう織物」へと読み替えられなければならない。
曆は現在、⻄洋のグレゴリウス暦に統⼀されて全世界で⽤いられているが、他⽅でそれぞれの地域ごとに固有の曆もまた並存している。⽇本においても明治期の欧化政策のなかでグレゴリウス暦への転換が⾏なわれた。しかし、現在の⽇本において実際の⽣活様式においては、固有の曆にしたがっている。各地の伝統芸能は旧暦にしたがって執り⾏なわれるため、その芸能が共同体の中でもつ意味は継承されている。
伝統芸能は曆どおりに実現されることが求められるので、そのための準備が必要である。これは⾳楽演奏や種々の舞台公演と同じである。まさにそのために⼈々の⽇々の営みもまた決定されてゆく。カトリック教会のミサもまた同様で、典礼暦に則って粛々と準備が重ねられ、その当⽇のミサが執り⾏なわれる。曆は時間の周期であり、⾳楽はそれ⾃体の思考と⾔葉によって、その周期を綴ってゆくのである。
キーワード:時間、曆、典礼暦、ミサ聖祭、伝統芸能
「音楽から人/ひとを考える会」第33回を開催します。
日時:10月16日(水)20時~22時頃
形式:Zoomによるオンライン(URLは下記参照)
発表者:安原道子氏
題目と概要:ラジオ放送局開局初期の放送で電波にのった音楽
―放送された民謡と演奏者を中心に―
ラジオ放送が始まってからは、検閲も厳しく、歌詞がある邦楽は、三味線音楽も民謡も、事前に歌詞を削除したり、書き換えたり、時間の制約があり、ということで、所謂それまでに受け継がれて来た音楽ではなくなっている。それでも、かつてのように必要な場で見聞きする機会がない者にとっては、初めて耳にする音楽である。
現在の民謡は、放送開始とともに作り出された音楽でもある。民謡教室があり、民謡大会に出場する方もいるので、今でも歌われているが、いわゆる演奏会用の民謡といっていいのかもしれない。
もう一点は、レコード、ラジオ放送とともに、芸妓の職業のあり方に変化がおとずれ、演奏者として独立する機会を得たことである。ラジオ放送開始から芸妓さんは出演しているが、東京放送局では邦楽の流派の一員として出演しており、九州のラジオ放送では、検番名と芸妓名が新聞でも大きく紹介されており、個人に目を向けてもらう機会を得ている。
ラジオ出演者は、文献においても、新聞紙上でも演奏者=「放送者」という表現が使われている。「放送者」には、邦楽の専門家、検番(券番、見番)に所属する芸妓衆という職業演奏家と、地元の有志、小学校の児童も存在する(井上精三、1962)。昭和3年熊本放送局開局から昭和5年福岡放送局開局時の邦楽の種目と出演者決定についての状況が、当時の福岡放送担当者井上精三氏によって記載されている。また日本放送協会による『昭和十一年 ラジオ年鑑』)に「放送新人の募集」の記事が掲載されており、種目ごとに応募者と合格者名が記載されているので、電波に乗せられた音楽と出演者の参考とする。
「音楽から人/ひとを考える会」第32回を開催します。
日時:9月18日(水)20時〜22時
形式:オンライン形式
報告者:永原恵三
課題:今後の会の運営について
「音楽から人/ひとを考える会」第31回を開催しました。
日時:7月17日(水)20時〜22時
形式:オンライン形式
報告者:安原道子氏
題目:NHKラジオ放送局開局初期の放送で電波にのった音楽
ー放送された民謡とその演奏者を中心にー
コール淡水・東京 第11回定期演奏会を開催します。
日時:2024年6月2日(日)14:00開演
場所:トッパンホール(飯田橋または江戸川橋下車)
入場無料(定員制ですので、入場券が必要です。)
入場を希望される場合は、下記の永原アドレスまでご連絡ください。
k-nagahara@ouj.ac.jp(永原恵三)
チラシはこちら
「音楽から人/ひとを考える会」 第30回を開催します。
日時:2024年5月15日(水)20時〜22時頃(途中入場、退場はご遠慮なく)
形式:オンライン開催
報告者:田辺沙保里氏
題目:ドイツ語圏における浄瑠璃の受容 -2003年の竹本千歳太夫に関するラジオ放送を中心に-
報告概要:
発表者は、比較音楽学の起点である独語圏において、雅楽、声明、平家、能楽、浄瑠璃、歌舞伎等の日本の伝統的な音楽種目が「仲介者」の手により、どのように伝達されてきたのか、というテーマに関心があります。
本発表では、まず日本音楽に関する独語文献における浄瑠璃の位置付けを概観し、一例としてアドルフ・フィッシャーの記述(1900年)を取り上げます。当時の言及はいずれも断片的で、現時点で纏まった論考の存在は認められず、1970年代に義太夫節の研究を開始したハインツ=ディータ・レーゼ(Heinz-Dieter Reese 1952-2024)が、ドイツ語圏で初めて文楽の音楽的側面に着目した先駆的存在であると考えられます。
発表の中心として、そのレーゼによって制作された竹本千歳太夫に関するラジオ番組(Die Stimme als Spiegel der Seele -Ein Portrait des japanischen Bunraku-Sängers Takemoto Chitosedayû-, 2003年11月22日バイエルン放送)を分析します。番組は、奏演・詞章の翻訳・インタビュー・解説という4つの要素で構成されており、表現技法等の音楽的観点への着眼が鋭く、聴きどころに集中させる鑑賞の手引きとして機能し、奏演者への聞き取りによって伝習方法等の舞台からは見えない背景にも迫っていることが特徴的です。
大変残念なことにレーゼ氏は今年2月に急逝されました。今後は彼が残した義太夫節の研究について更に調査を続けたいと考えております。
(尚、本発表は3月9日に行われた日本民俗音楽学会第12回研究例会での内容です。)
本日、メンバー以外で参加を希望される方は、永原恵三(k-nagahara@ouj.ac.jp)までご連絡をお願いいたします。
「音楽から人/ひとを考える会」第29回を開催しました。
日時:3月20日(水)20時〜22時頃(途中入場退出はご遠慮なく)
形式:オンライン開催
報告者:上西久美子氏
題名:万葉集における紐を「結ぶ」「解く」
概要:前回同様、折口信夫を皮切りに、紐を「結ぶ」という行為に込めた思い、および「解く」の意を見る。そして、日本神話からまつわる思想、七夕の歌などの類歌を概観する。また、現代に残る風習についてのフィールドワークを報告する。
放送大学 東京文京学習センター 永原ゼミ 成果発表演奏会を開催しました。
2024年3月17日(日)15時開演
会場:アカデミー向丘レクリエーションホール
チラシはこちら。
放送大学 東京文京学習センター 公開講演会を開催しました。
2024年2月10日(土)永原恵三 公開講演会 https://www.sc.ouj.ac.jp/center/bunkyo/news/2024/01/12112959.html
会場:放送大学東京文京学習センター多目的講義室1
題目:「《アヴェ・マリア》の歴史を歌曲でたどるーグレゴリオ聖歌からシューベルト、そして現代カトリック聖歌まで−」
概要:聖母マリア賛歌として知られる《アヴェ・マリア》は数多くの作曲家によって作られ、親しまれている曲も多いですが、起源はグレゴリオ聖歌にあります。近年は西洋中世史の分野で優れた研究もなされています。本講演では、その歴史を録音や実際の演奏でたどり、ラテン語の言葉の意味を理解します。さらに、ドイツ歌曲となっているシューベルトの《アヴェ・マリア》についても、その意味を考えてみます。
当日配付資料:
2023年12月19日 「音楽から人/ひとを考える会」第28回を開催します。
日時:12月20日(水)20時〜22時頃(途中入場、退出はご遠慮なく)
形式:オンライン開催
報告者:海野るみ氏
概要:「うたの所有についての考察 Ownership of songs 」
南アフリカ・グリクワの人々のうた/うたうことや讃美歌の合唱についての認識を再検討します。
会員以外で参加を希望される方は、以下のアドレスまでご連絡ください。
k-nagahara@ouj.ac.jp
2023年11月14日 「音楽から人/ひとを考える会」第27回を開催します。
報告者:安原道子さん
題目: NHK ラジオ放送局開局放送で電波に乘った各地の民謡
‐九州の NHK ラジオ放送局開局時の出演者と選曲‐
概要:
大正 14(1925)年 NHK ラジオ東京放送局(JOAK)開局から始まった各県の開局記念番組では、邦楽、民謡、西洋音楽、新日本音楽が放送された。各地の音楽を、多くの人が同時に聞くことができる空間が大きく変化したのである。ラジオ出演者は、文献においても、新聞紙上でも演奏者=「放送者」という表現が使われている。
「放送者」には、邦楽の専門家、検番(券番)に所属する芸妓衆という職業演奏家と、地元の有志が存在する。また、 その地の各小学校の児童が独唱、斉唱をしている。 「児童の放送は、家庭のラジオに対する関心を高めるのに大いに役立った」(井上1962:97)。
本報告では、主に邦楽、民謡の放送者に焦点をあて、放送される際に番組制作者による選曲と放送者の選出に対する認識および視聴者の要望を、福岡放送局開局当時の状況が書かれた文献を分 析することで明らかにすることを目的とし、その後、現在に繋がる民謡愛好者と職業演奏者の活動状況 を考察する際の一助とするものである。
★メンバー以外で参加を希望される方は、永原恵三(k-nagahara@ouj.ac.jp)まで、直接ご連絡ください。URLをお送りいたします。
2023年10月18日 「音楽から人/ひとを考える会」第26回を開催します。
日時:10月18日(水)
報告者:澤田篤子氏
報告要旨:
報告者:澤田篤子氏
報告タイトル:日本の伝統音楽の研究者が社会に果たしうる役割
報告の要旨:
理系優先の昨今、人文学系に対する世間の期待は必ずしも高いとは言えません。2015年に文部科学省が人文社会科学系学部大学院に対して組織を見直し、より「社会的要請」の高い分野への転換に積極的に取り組むよう要請しました。あとで弁解をしたそうですが、これは国の本音を示していると言えましょう。
私は日本の伝統音楽を主な研究対象とし、また音楽教育学では教育内容を主としていました。そのため、社会が音楽、特に伝統音楽に何を求めているのか、また伝統音楽の研究者はその「社会的要請」にどう対応でき、あるいは何を提言できるのか、また教育面では、子供達に伝統音楽の何をどのように伝えるのか、といった問いに向き合わざるをえないことがしばしばありました。
今年の東洋音楽学会大会のシンポジウム「研究者・伝承者・教育者の幸せな連携を考える?京都の六斎念仏をめぐって?」で、私は研究者の立場から発言することになりました。これも上述の問いの一環とも言えましょう。
今回は、この大会シンポジウムも視野に入れ、これまでの自他の活動や成果を振り返り、研究者ができること、すべきことについて、話題提供をさせていただきたく思います。そして、皆様のそれぞれのご専門の立場から、ご意見をいただき、さらに掘り下げていくことを願っています。
第26回に参加ご希望の方は、永原恵三(k-nagahara@ouj.ac.jp) まで、直接ご連絡をお願いいたします。URL等をお教えいたします。
2023年10月18日 「音楽から人/ひとを考える会」第25回を開催しました。
日時:9月20日(水)オンライン
報告者:岩本由美子氏
報告概要:
ドゥセク夫妻がコンサートで演奏したハープとピアノフォルテのための作品考察
ー「伴奏付ソナタ」にみられる音楽家同士(特に家族)による演奏サポートのあり方ー
本発表は、「ソナチネアルバムのデュセック」として親しまれているヤン・ラディスラフ・ドゥセク(1760-1812、以下ドゥセク)の作品研究の一環として、彼が妻ソフィア(1775-c1830)と演奏したハープとピアノフォルテのための作品(C170)を取り上げる。ヨーロッパ各地で作曲及び演奏活動を行ったドゥセクと彼の弟子の1人で1792年に妻となったソフィアは、それぞれ優秀な音楽一家に生まれ、当時ロンドンを訪れたハイドンら著名な音楽家たちと共にコンサートに出演し、多くの称賛を浴びていた。上記作品は夫妻が共に演奏した記録が残る2曲のうちの1曲である。この曲の出版譜(初版)は「二重奏Duet」のタイトルであるが、初演当日の新聞による演目紹介は、「弦楽やピアノフォルテによる伴奏の付けられたペダルハープのための大ソナタ」であり、演奏者が妻ソフィア、伴奏者がドゥセクと弦楽奏者とホルン奏者たち、と記されていた。本研究者は、この曲が当時ロンドンで流行していた「伴奏付ソナタ」であるという点に特に着目し、音楽家たちが共に演奏し合うことによって同業者(特に家族)の演奏をサポートするという当時の演奏の在り方を明らかにすることを試みる。
2023年9月6日 「音楽から人/ひとを考える会」第24回を開催しました。
なお、第25回は、2023年9月20日(水)20時開始です。概要については、後日掲載いたします。
日時:2023年8月30日(水)20:00(午後8時)開始
報告者:海野るみ
報告タイトル:「南アフリカ・グリクワの人々の歴史、場所、アイデンティティ」 (“History, Places and Identity of Griqua People in South Africa”)
報告要旨:
私がグリクワの人々の下でフィールドワークを始めたのは、南アフリカが民主的な統治を取り戻した直後のことである。国家としての南アフリカは、その過去と対峙し、解決しなければならなかった時代、グリクワの人々は希望と不安を抱いていた。そんな時、グリクワの人々は私を彼らのコミュニティに受け入れ、私に「グリクワの歴史」について学び、書くことを期待したのだ。
本論は、「グリクワの歴史」を理解しようとした、私の奮闘の記録である。また本論では、グリクワの人々が、彼らの歴史の「実践」を通して、どのように空間を拡張し、場所にタグ付けしているのかを記述する。ある地域とこの人々とを結びつけ、関係づけるような歴史を構築することは難しい。それは彼らが繰り返し、ある場所から異なる場所へ移動してきたからであり、南アフリカ社会の中でマイノリティであり続けたからである。同時に、彼らは彼らの歴史のなかで言及されるスポットにタグ付けし、そこを「グリクワの場所」と認識する。グリクワの場所は、南アフリカ全域、またはその国境を超えて散在する。そしてなお、グリクワの歴史実践において、散在する各所は関連し合い、彼らのアイデンティティを形作るのである。
経緯説明:
今回報告させていただく内容は、9月下旬に行われる国際地域史学会(International Society for Regional History, オンライン開催)で
英語での報告を予定しているものです。同学会は欧州やアフリカ、日本の地域史に関連する諸分野の研究者が昨年立ち上げた学会で、今回がキックオフの国際会議となるものです。(ご参考まで、会議のHPはこちらです。https://isrh.org/wp-content/uploads/2023/08/ISRH-Webinar-Programme.pdf)
今回のオトヒト会での報告では、グリクワの人々の音楽的行為をある程度、後景にもっていきつつ、しかしながら彼らの歴史実践が「合唱」や「賛美歌」やうたうという行為を抜きにしては語れないことも明示しつつ、幅広い分野の方々にも分かりやすく論旨を展開していく構成の仕方などをご相談できればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
2023年7月18日 「音楽から人/ひとを考える会」第23回を開催します。
7月19日(水)20時~22時30分頃(オンライン)
会員以外で、HPをご覧になって、参加を希望される方は、永原の下記アドレスまでご連絡ください。URL等をお知らせいたします。
E-mail:k-nagahara@ouj.ac.jp(永原恵三)
<発表者> 大沼薫 様(ハンブルク大学)
<題目> ライプツィヒ聖トーマス教会合唱団プレクラスの音楽教育
―2023年5月10日~13日の現地調査に基づいて―
<概要>
本発表では、2023年5月10日~13日に発表者自身で行った現地調査(音楽教員へのインタビュー及び授業見学)に基づき、ライプツィヒ聖トーマス教会合唱団(1212-)の伝統と音楽的水準保持の下支えとなっているプレクラスの音楽教育の内容・方針・目標を紹介することを目的とする。
聖トーマス教会合唱団は、16世紀の宗教改革以来、ライプツィヒ市有の合唱団である。市民の税金を活動資金の基盤とし、約100人の10歳~19歳の少年・青年たちが団員専用の寮で共同生活を送りながら、専門的な音楽教育を受けている。合唱団の主な任務は、聖トーマス教会で毎週金曜日~日曜日に行われるモテットと礼拝での音楽奉仕である。
合唱団維持のための基盤を成しているのが1990年の東西ドイツ統一後に設立されたプレクラスである。小学1年生~3年生の少年たちが、入団試験準備のため、合唱団の音楽教員による3年間の専門的な音楽教育を受けるシステムが構築された。プレクラスとして最も重要なアンナ・マグダレーナ・バッハ小学校の音楽クラスでは、音楽の授業は週に4時間行われている。授業は音楽理論と合唱練習で構成される。これに加え、週に1回30分の声楽・ピアノの個人レッスンも無料で提供される。入団試験では、声楽・ピアノの演奏に加え、聴音や視唱も課題となるため、理論と実践両面を重視した教育内容となっている。少年たちが身に着けなければならない能力は、合唱団の音楽的水準保持だけでなく、その忙しい音楽活動にも欠かせないものだ。というのも、合唱団はモテットや礼拝のために新しい曲を毎週何曲も習得することを求められ、同時に、国内外の公演や教会暦に合わせてヨハン・セバスティアン・バッハの《マタイ受難曲》や《クリスマス・オラトリオ》等を準備しなければならないからである。
今回の調査を通して、プレクラスは合唱団の存続にとって必要不可欠であり、その授業内容は合唱団で歌うことを第一優先にしたものであることが明らかとなった。
2023年6月26日 カトリック浅草教会『教会報』5月号、6月号に「教会と音楽」第17回、第18回を掲載しました。
カトリック浅草教会『教会報』2023年5月号「教会と音楽第17回」
カトリック浅草教会『教会報』2023年6月号「教会と音楽第18回」
2023年6月26日 東洋音楽学会東日本支部第135回例会でオンライン発表します。
2023年7月1日(土)
題目:「第二バチカン公会議以降における日本のカトリック聖歌について
−儀礼としてのミサの流動性と典礼暦との観点から−」
東洋音楽学会東日本支部のページをご覧ください。
http://tog.a.la9.jp/higashi/index.html
非会員で参加希望の方は6月27日までにお申込みください。
なお、発表原稿は後日、本Webサイトで公開します。
2023年6月26日 講演会に登壇しました。放送大学東京足立学友同窓会主催
「音楽をアンサンブルから理解するー民族音楽学が切り拓いた音楽の学びー」
2023年6月26日 演奏会に出演しました。「永井和子Presenz habe Dank 2! 〜真の歌声を求めて〜」
2023年5月20日(土)15:00開演
ザ・フェニックスホール(大阪)
「永井和子Presenz,habe Dank 2!〜真の歌声を求めて〜」に出演
演奏曲:F. シューベルト〈夜曲〉op.36 Nr.2
チラシ
2023年6月20日 「音楽から人/ひとを考える会」第22回を開催します。
6月21日(水)20時~22時30分頃
会員以外で、HPをご覧になって、参加を希望される方は、永原の下記アドレスまでご連絡ください。
E-mail:k-nagahara@ouj.ac.jp
<発表者>朴景蘭 様
・テーマ:(仮)「崔承喜(サイ・ショウキ、1911-1969)舞踊の「独自性」についてー「剣舞」(コンム)を中心に」
・概要:
本研究では韓国舞踊の中で長く踊られている「剣舞」に焦点を置きながら、崔承喜(以下崔に称する)舞踊はどのようなものであるかを明らかにしたい。崔の舞踊の「伝統性」を探ることは崔の舞踊の「独自性」に繋がると考え、まず、崔の舞踊動作に組み込まれている要素を確認する。
そのため、崔が「剣舞」を踊った時期を2つに区分し、(1)日本で活動していた時の「剣舞」と、(2)北朝鮮に渡ってから教本として残した「剣舞」に着目した。
(1)日本で活動していた時の「剣舞」については、2022年の国際高麗学会で、崔が1934年に日本青年館で発表した際の「剣舞」の写真と、1942年に日本で公演された「剣舞」の歴史と作品に関する意図を綴ったパンフレットが公開されており、それらを元に「剣舞」から見る崔の舞踊の「伝統性」を明らかにした。
(2)北朝鮮に渡ってから教本として残した「剣舞」については、現在、確認が取れる「剣舞」の映像は崔が1946年に北朝鮮へ渡ってから創作したとする舞踊劇「沙道城(サドソン」物語」の映像で、その中の50秒ほどの映像を見ることが出来る。北朝鮮の関係者は「剣舞」は現在も踊られているが、崔の作品は汲まれていないとした。
そのため、崔が執筆した『朝鮮民族舞踊基本』(1958)の「剣舞」の基本動作を在日舞踊家の協力を得て、動作の復元をし、その再現動作を元に動作分析を行っている。共に、比較対象として在日韓国舞踊家にいくつかの動作を試してもらい、動作を行う時の重力の移動、呼吸方法などを確認している。
本発表では崔は「剣舞」に伝統的要素をどのように組み込んでいるのか、また(できれば)、韓国舞踊の美的概念である「興」をどのように表現しているのかを確認したい。
2023年5月10日 「音楽から人/ひとを考える会」第21回を開催します。
5月17日(水)20時~22時30分頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、
どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
●話題提供 笠井津加佐様
●テーマ
「文学作品に記載された音楽情報について-吉屋信子作『女人平家』を事例に-」
●概要
「私は子供のころから、時代劇や歴史小説、また歌舞伎や文楽を観るたびに、いわゆる史実との距離を感じて参りました。今回私は、この距離のことを少し考えてみたいと思います。対象作品は『女人平家』という、女性中心に描かれた平家の栄枯盛衰を物語るお話ですが、用例として作品を取り上げさせていただくばかりで、作品研究ではございません。
文学作品から歴史的な音楽情報を収集することの可能性と問題点の抽出が話の中心でございます。作品には、読者が当時の音楽を想起するような記述が見られますが、それが史実に基づくのか、創作なのか、また、作者の単純な誤解なのか…などなどのことを考えたいと思います。そして、音楽に関するもの以外に見られる和歌の解釈のゆれを考えたり、代表的な登場人物については史料との比較を行うなど、可能な範囲で具体な事例を挙げて考えてみたいと思います。
今回、お目にかける作業は、私が、作品を読むために毎回行うものですが、用例では基本的なことを行いたいと思います。
報告と言うほどの纏まりのあるものでなく、ゼミの作品演習のようなものですが、こういった作業から音楽の研究が可能なのか、可能ならどんな研究ができるのかといった話題を提供できますれば、嬉しいことでございます。どうぞよろしくお願い致します。」
会員外で参加を希望される方は、直接永原までご連絡ください。URL等をお送りいたします。
連絡先:永原恵三 k-nagahara@ouj.ac.jp
2023年4月12日 「音楽から人/ひとを考える会」第20回を開催します。
4月19日(水)20時~22時30分頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、
どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
●発表者 持橋(根来)章子さま
●テーマ
「フランス近代音楽と東洋音楽研究の接続点:パリ・スコラ・カントルム
音楽院のグレゴリオ聖歌研究に着目して」
●概要
19世紀末頃からアジア音楽がフランスの音楽家たちに与えたインパクトは、
20世紀初頭には戯画的なエグゾティスムを超えて、アジア音楽の理論的消化と、
受容を正当化しようとする動向が見られるようになる。
その背景の一つには、ヴァンサン・ダンディらが設立したパリ・スコラ・カントルム音楽院における
グレゴリオ聖歌復興を目的とした研究・教育との結びつきを見い出すことができる。
アジア音楽の発見そのものよりも、フランスに内在するアジア音楽との親和性の発見が、
エグゾティスムの発展的消化の糸口となったことを、スコラ・カントルム音楽院の
機関誌等の分析を通して示したい。
★会員以外の方で参加を希望される場合は、永原(k-nagahara@ouj.ac.jp)まで直接ご連絡ください。
URLをお伝えいたします。
2023年3月9日 「音楽から人/ひとを考える会」第19回を開催します。
3月15日(水)20時~22時頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、
どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
1月第17回オトヒト会では、宮本常一著『忘れられた日本人』をテーマに、
参加の皆様より、様々なご発言が交わされました。
2月第18回オトヒト会では、1月のテーマの中から、安原が注目した内容を
取り上げました。「盆の口説き」が、安原にとっては経験のない事柄で注目しましたが、
取り上げた資料に対する説明不足を痛感致しました。
3月第19回オトヒト会は、メンバーの上西久美子さんが、読書会の内容から__
「歌垣」について話題提供をしてくださると、手を挙げてくださいました。
ありがとうございます。
●話題提供者 上西久美子さん
●タイトル
「古代文学の歌垣-三輪山をめぐる深淵-」
●概要
『万葉集』にはたくさんの歌垣が挿入されている。
しかし今回は、比較対照できる『古事記』『日本書紀』に残る歌垣を概観する。
そして、現代の万葉集学者がその起源で採用している折口説を見る。
●配布資料____
2部
★メンバー以外で参加を希望される方は、直接、永原恵三(k-nagahara@ouj.ac.jp) までご連絡をお願いいたします。
URL等をお送りいたします。
2023年2月14日 「音楽から人/ひとを考える会」第18回を開催します。
2月15日(水)20時~22時頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、
どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
(話題提供)安原道子
先月の読書会では、安原の研究テーマに関わる内容が多くありましたので、
あらためて、読み直しているところです。
*宮本常一 2021(1984)『忘れられた日本人』、東京:岩波文庫.900円+税、*
この中から、以下の項目より、注目した点を取り上げ、どのような研究ができるか、
について考えています。
①対馬にて(1.寄り合い、2.民謡):pp.11-35
②村の寄り合い:pp.36-58
③文字を持つ伝承者(1)、(2):pp.260-303
上記の(1)より(2.民謡)に、「対馬の北端には歌垣が現実にのこっていた」(p.32)と書かれています。
歌垣、掛け合い歌に関しては、梶丸氏が研究をされています。対馬の状況とは異なりますが、
論文をご紹介いたしますので、各自ダウンロードをお願い致します。
オトヒト会当日のレジュメは、開催日前日にあらためて送信させていただきます。
梶丸 岳
秋田県の掛け合い歌「掛唄」の今
民俗音楽研究 39(39) 49-60 2014年3月 査読有り
https://researchmap.jp/read0145036/published_papers/13412614
どうぞよろしくお願いいたします。
なお、会員外で参加を希望される方は、永原恵三の下記メールアドレスまで、
直接、ご連絡をお願いいたします。
*********************************
永原恵三
放送大学客員教授
(東京足立SC、東京文京SC)
Prof.Dr. NAGAHARA Keizo
k-nagahara@ouj.ac.jp
**********************************
2023年1月17日 「音楽から人/ひとを考える会」第17回を開催します。
1月18日(水)20時~22時頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、
どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
今回から新しい試みとして、「読書会」を発表の合間に挟んでいきます。
本研究会の「読書会」では、一冊の文献について、何回かに分けて、
出席者がそれぞれに当該箇所についてコメントをする、という形式を取ります。
発表ではありませんので、各人の立場でコメントを出していただければよいと思います。
初回は、対象となる文献の全体を通して、メンバーそれぞれで気になる箇所をとりあげ、
深掘りしたい部分を絞っていきます。
今回の対象本は、
宮本常一 2021(1984)『忘れられた日本人』、東京:岩波文庫.900円+税、です。
必要な方は、文庫本ですので、各自でご購入ください。Amazonで翌日入手できます。
稀少本ではないので、コピーは配信いたしません。ご注意ください。
メンバー以外でご参加を希望される方は、
k-nagahara@ouj.ac.jp(永原恵三)まで、直接ご連絡をお願いいたします。
2022年12月15日 「音楽から人/ひとを考える会」第16回を開催します。
12月21日(水曜日)20時~22時頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、
どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
題目:芸術における真実性あるいは現実性(芸術の真実と現実を問う シリーズ3)?聖歌"Ave verum corpus"の音と言葉
担当:永原恵三
概要:
キリスト教(とくにカトリック教会)において、"Ave verum corpus"の祈りの言葉から、グレゴリオ聖歌以降数々の名曲が生まれました。
"Ave verum corpus"とは、「Ave verum corpus まことの御体」をインチピットincipit(冒頭句)にもつ聖体賛歌の一つです。
今回は、この聖体賛歌のラテン語を読み、その意味(語義だけでなく、神学的な解釈も含めて)をミサという典礼あるいは儀礼のなかで考えます。
また、グレゴリオ聖歌、ウィリアム・バード、モーツァルト、などの楽曲をもとにして、音楽と言葉の関係をたどります。
なお、具体的な楽曲の考察については、全曲は無理なので一部のみにいたします。
これらの過程を踏まえて、音楽あるいは芸術がもつ真実性(Wahlheit)と現実性(Wirklichkeit)を検討したいと思います。
★ 会員外で参加を希望される方は、直接、永原恵三(k-nagahara@ouj.ac.jp)まで、メールにてご連絡をお願いいたします。URLとレジュメをお送りいたします。
今後の予定案
3回ぐらいを使って、読書会形式での研究会にしてはどうかと思います。
テキスト:宮本常一 2021(1984) 『忘れられた日本人』、東京:岩波文庫.
日本各地(とくに西日本)の民俗誌を集めたものですが、人びとの普段の生活の中にある「音楽」に関わる様々な記述が出てきます。
もちろん、「音楽」以外で気になる記述があれば、それを考えるのもよいと思います。
発表者の希望がない回に入れていくかたちを考えています。
2022年10月17日 「音楽から人/ひとを考える会」第15回を開催します。
10月19日(水曜日)20時~22時頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、
どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
題目:「愛好者による民謡の継承―福岡と長崎におけるNHKラジオ放送局開局時の演奏者と現在の事例から」
報告者:安原道子
(概要)
本発表では、芸能(民謡)の歴史的背景を踏まえつつ、現在、愛好者によって継承されている民謡の実情を、福岡と長崎の事例に基づいて報告する。
大正14(1925)年NHKラジオ東京放送局(JOAK)開局から始まった各地の開局記念番組では、民謡が取り上げられ、日本全国で聞かれるようになるという脈絡の変換が生じている。
九州では、昭和3(1928)年~8(1933)年の熊本、福岡、長崎のNHKラジオ放送局開局記念番組において民謡が演奏されたが、演奏者の大半が地元の検番に所属する芸妓衆であった。素人の出演者としては、熊本放送(JOGK)開局2日目に、福岡県早良郡脇山村(現・福岡市早良区脇山)の青年たちが「主基斎田御田植歌」を歌っている。「農村人としての九州におけるラジオの初出演者はこの人たちである」(NHK福岡放送を語る会編『博多放送物語』2002年)。また、昭和8年NHK長崎放送局開局記念番組においては、長崎市内の6つの検番および島原、大村から芸妓衆が出演しているが、「瀬戸ペーロン歌」は瀬戸村青年5人、「平戸自案和楽」は平戸町有志が出演している。
現在の長崎市では、検番の芸妓衆による演奏がホールなどの公開の場で催されている一方で、一般の人々による演奏活動も行われている。今回は、昭和初期からの長崎の芸能界の主流を引き継いでいる、長崎市在住の邦楽演奏者である丸木覚誠氏の協力を得ることができた。そのため、丸木氏主催の民謡サークルの活動および愛好者個々人の民謡習得と指導の過程における問題点を、計量音楽学の手法を取り入れることによって調査することで、継承されていることの可視化を試みる予定である。
なお、福岡に関しては、この夏に調査を予定していた事例が11月に延期されたため、今後の取り組みとする。
会員外の方は、直接、永原恵三(k-nagahara@ouj.ac.jp)まで、メールにてご連絡をお願いいたします。URLをお送りいたします。
2022年9月13日 「音楽から人/ひとを考える会」第14回を開催します。
9月21日(水曜日)20時~22時頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
報告者:岩本由美子
題目:1790年代のロンドンで作曲・演奏された「ロンド」について
報告者は、1790年代にロンドンで音楽活動を行ったJ.Lドゥセク(J.L.Dussek)を研究しています。ドゥセクは、現在日本では、ソナチネ作曲家としてのデュセックDussekとして、または、チェコ出身のドゥシーク Dusikとして知られていますが、当時は、ヨーロッパ各地で名を馳せた、優れた作曲家および器楽奏者(ピアノフォルテ)の1人でした。ロンドンは、ドゥセクが人生で最も長い時期(1789-99年、約11年)を過ごした場所であり、その時期のイギリスは、ちょうど、フランス革命戦争を戦っていました。
昨年9月の発表では、ドゥセクらの当時の器楽曲に、史実(=戦い)に関するものがあり、その類の器楽曲には、現代の英国国歌にあたる《God save the King》や《Rule Brittania》が挿入されていた、という事象を取り上げました。
今回注目するのは、「ロンド」という作品群と、それに関する人気の歌airについてです。本発表では、これらのロンド作品が、単にロンド形式であるというより、当時のイギリスにおける、国民歌(National Air、例えば上記2曲)や周辺地域(スコットランド、ウェールズ、アイルランド)のエアairや、またはダンス曲(リールreel)等がテーマとして使用された、ということが主だった特徴の1つであることについて報告を行い、このような作品群 が、ドゥセクを含む、当時著名であった音楽家(器楽奏者、歌手)によって、どのように出版され、どのようにコンサートに取り上げられたのか、ということも資料から辿りたいと思います。
「ロンド」という、ありきたりな音楽用語(形式)の概念を超えて、幅広いご意見・ご指摘、今後の研究可能性についてのご助言等頂戴できれば幸いです。
会員外で参加を希望される方は、永原恵三のアドレス(k-nagahara@ouj.ac.jp)にご連絡ください。URLをお送りいたします。
2022年8月12日 「音楽から人/ひとを考える会」第13回を開催します。
8月17日(水曜日)*20時~22時頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
8月の話題提供は、余静嘉さんが手を挙げてくださいました。ありがとうございます。
事前資料はございません。
テーマ:『論語』における孔子の音楽実践と音楽の特徴
報告者は、中国思想にある音楽と感情の関係性について研究しております。今回は中国儒家思想の著作『論語』の音楽についての研究を発表したいと思います。『論語』では音楽に対する具体的な定義がありません。しかし、孔子はかなり音楽を重視しており、自らも音楽を実践して、また音楽の特徴、音楽の機能などについて、『論語』の中及び孔子に関する文献の中に散見しています。
土田健次郎『儒教入門』にも、音楽は「礼」と一緒に重要な位置を占め、「儒教にとっても必須の領域であった。」と説明がありました。
今回は『論語』を中心として、孔子がなぜ音楽を重視しているか、音楽に対する態度や彼における理想の音楽像について分析します。
今回の報告にも言及しますが、中国古代音楽論には「音楽」と「心(主に感情)」の関係性が重要な課題になっております。これらについて、中国音楽のみならず、各視点からの考え方を吸収したいですので、皆様のご意見を頂ければ幸いです。
(余さんの自己紹介は、7月11日のお知らせに載せておりますので、ご確認お願い致します)
2022年7月15日 「音楽から人/ひとを考える会」第13回を開催します。
7月のオトヒト会は、お休みです。
次回第13回は8月17日(水曜日)20時~22時頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
(話題提供) 余 静嘉様
「『論語』の音楽について」
(余 静嘉様 自己紹介)
2019年にお茶の水女子大学大学院修士課程を修了し、現在東京大学大学院中国 思想文化学研究室に研究生として所属しております。中国の音楽美学、特に音楽と感情の関係性に関心があり、修士論文では中国の音楽美学著作『楽記』について執筆しました。いまは中国の春秋戦国時代の音楽に関する言説(主に儒家)を研究しています。よろしくお願いいたします。
※話題についての概要は、8月に入りましてから改めてお知らせいたします。
〈嬉しいお知らせ〉
オトヒト会、正式名称「音楽から人/ひとを考える会」は、東京文化会館会議室の使用団体登録を申請していました。使用団体には「芸術文化団体」と「一般団体」の二種類があります。この一年の活動内容から、「芸術文化団体」として承認されたことをご報告いたします。オトヒト会は、永原先生を中心に、広範囲の方々とオンラインで繋がっているゼミですが、対面で集まることができる日も来ることを、楽しみにしています。
オトヒト会の足跡は、永原先生のホームページをご覧ください。
http://nagahara-otohito.com/
(連絡係)
安原道子
お茶の水女子大学基幹研究院研究員
2022年6月13日 「音楽から人/ひとを考える会」第12回を開催します。
第12回オトヒト会
6月15日(水曜日)20:00~22時頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
会員外で、参加を希望される場合は、
nagahara@kxa.biglobe.ne.jp(永原恵三)まで
直接ご連絡ください。URLをお送りいたします。
話題提供 海野るみ様
「研究ノオト:雑誌『通俗新樂譜』『通俗音樂』をながめる」
報告者は、明治後期から大正期に教育者、音楽家、文筆家として活躍した(と思われる)黒木寛(耳村)についての研究を進めています。
今回は、彼が編集主幹として関わった雑誌『通俗新樂譜』『通俗音樂』を取り上げます。
(なお、『通俗音樂』は『通俗新樂譜』の改称後の名称です。)
大正3年に発刊された同誌は、当時の社会的背景を反映した通俗教育(社会教育)政策の推進に呼応したものではなかったかと考えられます。
今回は研究報告の前段階として、まず明治から大正期における「通俗教育」の展開の概略を解説した後、
これまで研究対象としての事例が見られない雑誌『通俗新樂譜』『通俗音樂』をご紹介します。
その上で、今後の研究の可能性についてお話し、皆様のご助言やご指摘をいただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
海野るみ
2022年5月20日 「音楽から人/ひとを考える会」第11回を開催します。
第11回オトヒト会
5月18日(水)20時~22時頃 オンラインで開催します。
会員以外で参加希望をされる方は、直接、永原恵三まで、以下のアドレスにご連絡ください。
nagahara@kxa.biglobe.ne.jp
(概要)
ここ数回のやや美学的な概念の提起からはかなり柔らかい内容にしてみました。
いろいろと考える糸口があるように思います。
使用資料は、久保田敏子・藤田隆則編、2008『日本の伝統音楽を伝える価値ー教育現場と日本音楽』京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター 所収、藤田隆則 「身体による伝承と習得ー古典音楽を中心に」33ー37.です。
メンバーの皆さまが研究しておられる分野に引きつけていただき、「音楽を伝えること」、「音楽を教えること」、「音楽を研究すること」それぞれの間で、関係性の糸あるいは網の目(ウェブ)はどのように張り巡らされるのか、また、この網目のなかで「身体」はどこに位置するのか、考えてみたいと思います。
今回の資料は2004年から2006年にかけて京都芸大の日本伝統音楽研究センターで開かれたプロジェクト研究「教育現場における日本音楽」の報告書ですが、ここで日本音楽について考えられたことは、西洋音楽のみならず現在研究されているさまざまな音楽についても考えるべきことと思います。
各メンバーの具体的な研究対象自体は全く異なりますので、議論の収斂は目指していませんが、いつものようにさまざまな考え方を共有できればありがたいです。
2022年4月18日 「音楽から人/ひとを考える会」第10回を開催します。
第10回オトヒト会から、開催曜日を第3水曜日に変更いたしますので、ご留意ください。
4月20日(水)20:00~22:00頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
会員外で参加希望の方は、永原恵三(nagahara@kxa.biglobe.ne.jp)まで、直接ご連絡をお願いいたします。参加料は無料です。今回は、永原がテーマを設定しました。年度初回ですので、皆様と自由に話し合う回にします。
以下、①今回のテーマ、②今後のオトヒト会(音楽から人/ひとを考える会)の趣旨、です。
①テーマ:資料から見える音楽の現実と非現実
概要:
新しい年度が始まりましたので、今回は発表形式ではなく、参加者の皆さんがご自身の研究のなかで考えておられることや、疑問に思っておられることを自由に話し合う回に(会に)しようと思います。あらためて、自己紹介というかたちでも構いません。今、このような研究テーマを扱っている、あるいは扱う予定、でもよいです。ただ、あまりに自由なのもお互いの理解に際限がありませんので、「資料から見える音楽の現実と非現実」という共通のテーマを設定してみました。これは前回、前々回の「芸術の真実性と非真実性」からの流れです。音楽学にせよ芸術学にせよ学問の一領域である以上、その対象となる「資料」(source)があると思います。それは必ずしも書記性によるものでなく、口頭性による「資料」も考えられます。音それ自体を「資料」と考えることもできます。たとえ、哲学や美学などの思弁的な領域であったとしても、テクストや言葉という資料があります。音楽や芸術の研究は必ず具体的な資料があってはじめて議論が成り立つと思います。しかしながら、同じ資料としての音楽や芸術と言っても、そこから何を読み取っているのか、基本的なことですが、読み取られている音楽は読み取っている側(研究者、演奏者、聴衆など)とどのような関係にあることを前提としてその読み取りの行為を正当化するのか、はその読み取りの言説をさらに読み取る文脈の中で、音や音楽はどのように語られて いるのか、現実と非現実とは分離されているのか、それともある程度の融合を了解の上で語られるのか、様々な段階があるように思われます。
②オトヒト会(音楽から人/ひとを考える会)の趣旨(案)
オトヒト会(「音楽から人/ひとを考える会」)はお茶大在職中の「通称金ゼミ」を継承するかたちで、新たな研究会として発足しました。全国あるいは世界 各地からの参加者を対象とするために、オンラインで開催します。学会発表や論文投稿の前に意見交換ができる場、研究途中で参加者の皆様からご意見をいただきたい方の発表の場、さらには、音楽学と関連諸分野(舞踊、美術、芸術学など)の研究者が気兼ねなく忌憚なく、その研究を共有して意見交換のできる場、として開かれた研究会になることを願っています。中堅やベテランの研究者のためにも、研究の継続や新しい分野への開拓など、また長い研究歴の中で気になっていたことなど、それぞれの世代の研究者が持つ課題を共有して、お互いの学問的理解を深める場になれば、誠に幸いです。昨今の学会や研究会は、基本的に若手研究者の発表を聴き、中堅やベテラン研究者がアドバイスするというかたちになっていますが、逆に、中堅以上の研究活動を自由にあるいは気兼ねなく発表したり、話題提供したりする場が意外に少ないように思います。大学の教育や雑務で疲れたけど、あるいは退職して時間はあるけど、気楽な発表の場があると少しは前進するかもしれない、と思う方々にも、ぜひ参加していただきたい、と思います。発表の仕方の基本としては、事前(1週間ぐらい前)に資料をメンバーに配布しておいて、あらかじめ目を通してもらい、その資料を用いて当日発表するというかたちです。その資料をどのように用いるかは発表者に任せ、当日はオンラインですので、パワーポイントでもよいですし、ワードのファイルに書き込みながらの発表でもよいですし、その方法は研究対象によると思いますので、ご自由にお 願いします。学会発表のような定型でのご発表である必要はありません。極端に 言えば、結論がなくても大丈夫です。
皆様の参加をお待ちしています。(主宰者:永原恵三)
2022年3月15日 「音楽から人/ひとを考える会」第9回を開催します。
オトヒト会第9回2022年3月17日(木)20時〜22時頃
(ご都合による開始時刻より遅れてのご入室、早目のご退出は、どうぞお気兼ねなくご参加ください。)
会員外で参加希望の方は、永原恵三(nagahara@kxa.biglobe.ne.jp)まで、直接ご連絡をお願いいたします。参加費は無料です。
話題提供:澤田篤子先生
題目:「仏教儀礼における恋慕渇仰の表現」
概要:
オトヒト会第8回(2月17日、釈迦涅槃日の2日後)の永原先生の「マグダラのマリア」についての記述と解釈」を仏教の場合と重ねながら受講させていただきました。マグダラのマリアからは、苦行中の釈迦に乳糜を献じ、後に初の在俗女性信者 (優婆夷)となったとされるスジャータ(須闍多)が、そして、聖母マリアから は、釈迦の母、摩耶夫人が想起されました。聖母マリアは美術や音楽で数多く表現されてきましたが、摩耶夫人は、少なくとも日本では、美術・音楽での表現例が非常に少なく、また摩耶夫人を主体とする儀礼も管見では一例のみです。日本では釈迦との母子関係性において描かれ、涅槃図や金棺出現図、中世の唱導の題材にもなっています。しかし、音楽の場合は、仏教儀礼ではどうも見当たりません。涅槃会で唱える明恵(1173-1232)作《四座講式》では涅槃・羅漢・遺跡・舎利の四講式が唱えられますが、中でも白眉とされる〈涅槃講式〉の入涅槃や金棺出現の場面でも摩耶夫人は一切描かれていません。明恵は彼自身の釈迦への強い恋慕渇仰の表現に集中したためでしょうか。明恵は涅槃会で自ら〈涅槃講式〉を唱えましたが、入涅 槃を叙述する場面で感極まり泣き咽び、弟子が代わって唱えたという話が伝えられるほどです。このような表現を可能にしたのは声の音楽としての講式の旋律構成法であり、この構成法を生み出し、儀礼という聖なる場に人間の率直な感情表現を包摂していった背景についても考えていきたく思います
澤田篤子先生のご紹介
澤田篤子先生(大阪教育大学名誉教授)
お茶の水女子大学の卒業生で、大学院修士課程ができた時に徳丸吉彦先生のご指導の下で、声明に関するご研究をされ、柴田南雄のいわゆる骸骨論を用いることによってその旋律組織を解明する、という先端的ご研究を発表されました。大阪教育大学に奉職後は声明研究だけでなく、音楽教育の分野で力を発揮され、日本音楽の学校教育への導入では中心的に活動されました。さらに平成13年から15 年の科研「薬師寺最勝会の形成過程の研究ー儀礼・音楽における伝承・創造の視座から−」で大きな成果を出され、「薬師寺「最勝会」復興上演」では平成15年度文化庁芸術祭賞大賞を受賞されました。このように理論と実践の両面でのご研究をされた上で、令和2年3月に学位論文『平安期から鎌倉期における声明理論の形成過程ー『悉曇蔵』および『声明用心集』を中心としてー』にて、博士(人文科学)(お茶の水女子大学)を取得されています。
(永原恵三)
2022年2月15日 連載エッセイ 音楽学者のつれづれ 第3回
2022年2月15日 「音楽から人/ひとを考える会」第8回を開催します。
オトヒト会第8回2022年2月17日(木)20時〜22時頃
話題提供者:永原恵三
題目:「マグダラのマリア」についての記述と解釈
概要:
今回は、直接に音楽ではないですが、美術や音楽などで取りあげられることの多い、「マグダラのマリア」についての記述と解釈、について考えます。最近、カトリック系の雑誌の『福音宣教』に「マグダラのマリア」についての、二人の女性の聖書学者からの論考が出ていて、『聖書』という流動的なテキストに対して、何が事実で何が解釈なのか、問題点を指摘しておられて、学問的に大変興味 深く思っています。具体例として、音楽史で有名なグレゴリウス1世や作家の遠藤周作も登場します。「マグダラのマリア」は絵画や音楽でも「娼婦」として登場しますが、実に大きな誤解だとわかります。芸術のなかで取りあげられる「歴史」の非真実性が興味深いですね。もちろんジェンダー論としてもなかなか厳しい指摘がありました。これらの論考と実際の『聖書』の記述とを照らし合わせて考えてみます。
資料は、遠藤周作、福島裕子、本多峰子、井上洋治の4氏によるマグダラのマリアについての論考(遠藤は小説)です。(奥付等含む)
遠藤氏は(カトリック)小説家、福島氏、本多氏は聖書学者、井上氏は司祭、です。
中心は福島氏と本多氏によるマグダラのマリアに対する解釈です。とくに新しい解釈ではありませんが、聖書のテキストに対して、多くの芸術作品が生み出されたテーマである「マグダラのマリア」について、学者として福島氏と本多氏が呈示するマグダラのマリア像は、もちろん、掲載された『福音宣教』の月間テーマ 「これからの教会と女性のために」という特集があるからこその内容ですが、今日の標準的な解釈と言えます。井上氏は司祭ですので、信者を中心とした一般向けの適確な文章です。
美術史の研究者である岡田温司氏の『マグダラのマリア』(中公新書)は、美術史の実証的な方法で説明している大変有益な書物です。絵画が主流なので具体的 によくわかります。
今回は、「マグダラのマリア」=娼婦=聖女という、ステレオタイプ化した公式に対して、『聖書』のテキストから読み取れる限りでの「マグダラのマリア」像を捉え直し、男性の使徒たちのなかでの女性の使徒の位置づけ、諸芸術におけるマグダラのマリアの表象、そして、芸術作品における真実性と非真実性について、考えてみようと思います。
2022年1月17日 「音楽から人/ひとを考える会」第7回を開催します。
新年の「音楽から人/ひとを考える会」第7回は、
2022年1月20日(木)20時〜22時頃(オンライン)です。
(ご発表者)
笠井純一先生(金沢大学名誉教授)、津加佐先生(金沢大学客員研究員)
(ご発表タイトル)
「花街舞踊復元の意義と可能性ー『北陽浪花踊』の映像資料と音源を素材としてー」
(添付資料)2点
1.発表用資料
「花街舞踊復元の意義と可能性ー『北陽浪花踊』の映像資料と音源を素材としてー」
2.参考資料
「住吉踊復元譜試作関係資料」
長い地道な研究と豊富な資料を元に、1時間ほどお話くださる予定です。
昨年秋の東洋音楽学会大会でのご発表を聞き逃した方はぜひご参加ください。
本会会員以外の方で、聴講を希望される場合は、
nagahara@kxa.biglobe.ne.jp(永原恵三)まで、ご連絡ください。
2021年12月13日 「音楽から人/ひとを考える会」第6回を開催します。
12月は、西阪多恵子さんが話題の提供をお申し出くださいました。
ありがとうございます!
第6回オトヒト会
12月16日(木)20時~22時頃
テーマ「19世紀末イギリスの音楽フィランソロピ(博愛活動)― People‘s Entertainment Societyを中心に」19世紀末のイギリスでは、貧困地域の人々に無料あるいはわずかな料金でよい音楽を提供しようとの活動が盛んに行われていました。そうした組織の一つPeople‘s Entertainment Societyは、音楽団体と慈善団体双方の性格を併せ持ち、雑誌等にみられるその記録は断片的ながら、当時の音楽観と階級など社会的な問題について、示唆を与えるものと思われます。この組織について紹介し、音楽文化におけるフィランソロピの意義などについて皆さまと共に考えたいと思います。
開催日の2,3日前にはレジメ(風)のものをお送りくださるとのことですので、あらためてご案内いたします。
お話を伺いながら、みなさまと話し合いができることを楽しみにしております。
2021年11月30日 連載エッセイ 音楽学者のつれづれ 第2回
2021年11月30日 連載講座 カトリック教会と音楽 第2回
2021年11月12日 「音楽から人/ひとを考える会」第5回を開催します。
第5回オトヒト会
11月18日(木)20時~22時頃
(発表者)安原道子
12月5日(日)に日本民俗音楽学会大会にて発表の機会をいただきました。
事前にオトヒト会の皆様からご意見、ご感想をいただけますことを願っております。
オトヒト会での発表レジュメは、現在準備中ですので、発表前日までに添付いたします。
今回は、大会プログラム掲載の概要を添付いたします。
2021年10月27日 連載エッセイ 音楽学者のつれづれ 第1回
2021年10月27日 連載講座 カトリック教会と音楽 第1回
2021年10月14日 「音楽から人/ひとを考える会」第4回を開催します。
第4回オトヒト会
2021年10月21日(木)20時〜22時
今回は発表希望者がいなかったので、永原から、毎度おなじみの「花輪ばやし」を題材に30分程度お話ししてみます。
題目は「花輪ばやし:音楽・プロパガンダ・ジェンダー」です。
参考文献は昨年度最後の金ゼミでも使用した、『都市の祭礼』の永原論文です。
同じ「花輪ばやし」でも写す側によって、当然写し方が変わります。
今回は、
1.花輪ばやしの音楽性はどこにあるのか。
2.プロパガンダとしての映像の特徴や目的はどこにあるのか。
3.民俗芸能のあるいは祭礼囃子におけるジェンダーをどこにどのように考察できるだろうか。
1〜3の関連性をどのように考えたらよいか。
以上を、議論したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2021年9月8日 「音楽から人/ひとを考える会」第3回を開催します。
第3回音楽から人/ひとを考える会(オトヒト会:新永原ゼミ)は、9月16日(木)20時〜22時頃 まで開催いたします。
当日ご都合がついた方、途中参加、途中退室は、どうぞお気兼ねなくご参加ください。
第3回「オトヒト会」
発表者 岩本由美子さん
題目:仮)1790 年代の英仏戦争と戦争のタイトルを持つピアノ曲、そして曲中に現れる国歌について
なお、会員以外で参加ご希望の方は、nagahara.keizo@ocha.ac.jp 永原恵三までメールでご連絡ください。
2021年7月2日 「音楽から人/ひとを考える会」第2回を開催します。
7月14日(水)20:00〜22:00頃、オンラインです。登録メンバー以外で、参加希望の方は問い合せフォームからお願いいたします。今回のテーマは「音楽を考える、を考える」です。参考文献は、椎名亮輔編著 2017『音楽を考える人のための基本文献34』、東京:アルテスパブリッシング。
2021年6月4日 「音楽から人/ひとを考える会」がスタートします。
6月11日(金)20時〜22時(オンライン)第1回を開催します。初回は顔合わせで、会の内容についての意見、希望を気楽に語り合います。第2回は「音楽を考える」とは???、をとりあえずのお題としています。参加を希望される場合は、問い合せフォームからご連絡ください。あらためてご案内を差し上げます。
2021年6月4日 放送大学東京文京学習センターの永原ゼミが再スタートいたします。
このゼミは放送大学の学生および卒業生(同窓会員)のみ参加できます。ご注意ください。参加希望者は問い合せフォームからご連絡ください。
2021年6月4日 放送大学面接授業の閉講
放送大学東京足立学習センターの面接授業(5月29日と30日)「音楽と身体」、および放送大学東京文京学習センターの面接授業(6月3日と10日)「音楽学概論」は、新型ウイルス感染防止のために、閉講となりました。受講を希望されていた方々には大変申し訳ありませんが、次の機会にお目にかかれることを願っています。
2021年4月1日 ホームページを公開しました。
2021年4月1日 ホームページを公開しました。